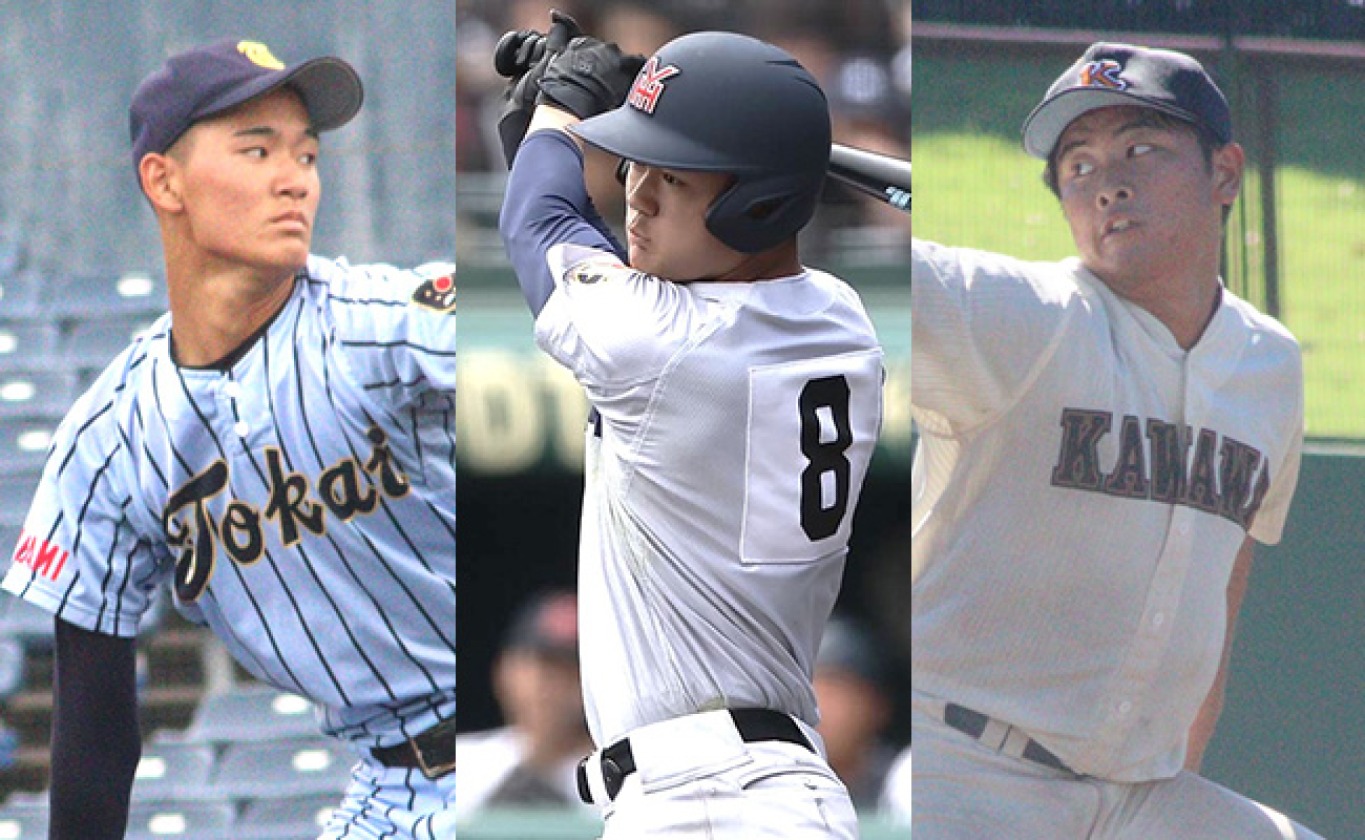新基準バットが導入されて2年目を迎える今シーズン。1年目を振り返ると、多くのチームが走塁を戦術として重視するようになってきた。そうなると、試合でも練習でも足腰を酷使することになるが、成長期にある高校球児は、未完成な体のためにケガに悩まされる選手が多い。
中学野球も同様の状況にある。高校生よりも未発達で、成長期にある中学生たちにも勝利と選手育成のバランスが求められる。
その点を成立させながら、走塁を活かして選手を育成する江東ライオンズの田本剛監督は、足腰のケガ人をほとんど出さない。
今回は、プレーヤーを道具で支えるアシックス・加藤祐也さんの2人に協力してもらい、指導法やケガ防止などを対談形式で伺った。
中学強豪が実践する走力強化
まずは練習法や指導法。発展途上にある中学生たちに対して、どういった練習をして走塁のチームを作り上げながら、ケガを防いでいるのか。最前線に立って指導する田本監督の意見は、現場を知る加藤さんも驚きのものだった。
――自身のチームはもちろんですが、大会などを通じて他チームとの交流をしていると、足腰のケガで悩んでいるチームは多いでしょうか。
田本剛監督(以下、田本):私のわかる範囲ですが、多いと思います。特にシンスプリントに陥ってしまう選手が多いように感じます。だから、私自身は足腰のケガに対してはものすごくアンテナを張っています。そのおかげもあってか、監督になってからシンスプリント、肉離れになる選手はいません。
加藤祐也(以下、加藤):シンスプリントを防ぐためのトレーニングをやって、シンスプリントを引き起こすケースもありますし、私自身もシンスプリントになったことがあったので、ケガ人が出ないことは非常に素晴らしいことだと感じます。
――普段の練習の成果であることは間違いないと思いますが、どういった指導をされているのでしょうか。
田本:シンスプリントを起こしてしまう選手は前脛骨筋や、その横にある腓骨筋といった脛骨や腓骨周りで炎症を起こしているからだと聞いたことがあります。それはストレッチがないからケガになってしまうと思います。ですので、腓腹筋とヒラメ筋といった後ろの部分の筋力で縄跳びをする。そうすると、ジャンプする時に脛骨や腓骨周りでストレッチが働くので、どちらも鍛えられるようになるのです。あとは筋肉の張り具合や筋肉痛の具合によって、ランメニューは変えるようにしています。
加藤:実は、足底からの圧力は非常に強力で 、それが足にかかる負担としてふくらはぎヒラメ筋から膝へと連鎖的に影響を及ぼします。 トレーニングを通じてしっかりと筋肉を伸縮させることでしっかりとした基盤を築き、ケガを予防することが重要だと思います。このような好循環は素晴らしく、非常に感銘を受けました。

――ランメニューの話が出ましたが、どういったメニューを組むのでしょうか。
田本:うちは走塁を強みにしていますが、走り込みはあまりやらないです。もちろん、人間は走ることが起源なので避けられないし、ある程度は必要です。ただ強度や量、頻度を私たちが限界を超えないように管理すればケガしないと思いますので、週1日で短距離や中距離。インターバル走で心肺機能とスピードを身につけます。
――トレーニングについては、どういったことに取り組んでいるのでしょうか。
田本:走るために必要な体幹や背筋をやります。またスプリットスクワットなどもします。あとはアップの中にドリルを入れて足の動かし方を覚えます。とにかくトレーニングで走る筋力をつけて、アップのなかでドリルをやってテクニックを習得する。これもあって、シンスプリントはもちろん、捻挫や腰椎分離症、膝の疾患もほぼいません。
実は田本監督、スポーツトレーナーの経験もあり、人体構造に対しては知識がある。ゆえに合理的なメニュー、指導法が実現している。ここに江東ライオンズの強さの一端が垣間見えた。