2022年パ・リーグ新人王&最優秀中継ぎ投手賞の西武・水上 由伸(帝京三ー四国学院大)らを輩出している四国地区大学リーグに新たな王者が誕生した。
その大学とは愛媛県松山市郊外にキャンパスを置く聖カタリナ大。元日本ハムファイターズ捕手の沖 泰司氏(現:ルートインBCリーグ・福島レッドホープス監督)を指揮官に迎え2018年創部。2021年春季の1部昇格からわずか9シーズン目の快挙である。
その反面、ここまでの道のりは決して平たんなものではなかった。草創期から身体能力の高い選手が多かったものの、主力選手が練習に参加せずシーズン途中で退部する事態は毎年の出来事。よって1部昇格後の成績も最下位こそなかったものの、優勝争いとは無縁。当時を端的に表現するならば半世紀前に愛媛県松山市郊外を舞台としていた漫画「アパッチ野球軍」さながらの状況が続いていた。
そんな淀んだ硬式野球部の空気を変えたのが東都の名門・亜細亜大出身の首脳陣である。2023年春に投手コーチから代行監督(翌年から監督)に転じた森 浩昭氏は、約30年間に渡るスポーツビジネス業のノウハウを活かし、まずは選手を食事に連れていくなど円滑なコミュニケーションを図った。一方で大分商では控えの内野手だった窪田 寛之投手(現:四国アイランドリーグplus・愛媛マンダリンパイレーツ)を最速147キロ右腕エースに育て上げ、投手強化の道筋を作ることに成功した手腕も快挙には欠かせなかった。
森監督からの要請を受け2023年にヘッドコーチに就任した佐伯 幸三氏は、西条ー亜細亜大ーJTー松山フェニックスと常に主力として活躍してきた。自身の経験を糧に「バットの重さを感じないような」スイング軌道と配球を読みながら最後は思い切りよく振る決断力で指導にあたっている。
加えて3年春から学生コーチに就任後「1人1人とコミュニケーションを取りまくった」田窪 将真(4年=松山中央)らも交えたチームビルディング策も功を奏し、昨年は春秋ともに優勝争いに絡み2位、3位の好成績を残した。さらに今季は昨秋シーズンⅤの高知工科大、数多くの部員を抱える松山大、四国学院大、オープン戦では好調だった愛媛大をいずれも2勝1敗で下す粘りを発揮。聖カタリナ大先勝のまま雨天により日程順延となった高知大戦を残した時点で、完全優勝に王手をかける格好となった。
そして迎えた5月10日の高知大戦。今季7勝のエース右腕・岩川 慎之介投手(4年=東温)を立てて臨んだ初戦を2対3で落とし、負ければ高知工科大に優勝を譲り渡す剣が峰で迎えたダブルヘッダーの2試合目で、またしても彼らは持ち前の粘りを発揮する。
投げては今季、右ひじ肘頭骨折から3季ぶりの復活を果たした先発右腕・髙橋 圭祐投手(3年=西条)が、「気持ちを強く持って」140キロ近くのキレのあるストレートとツーシーム・スライダーを低めに集め5回わずか51球無失点ピッチングで自軍へのリズムを形成。打っても西条時代の変則左腕投手から巧打者として再生を遂げた1番・門田 啓誠外野手(4年)の中前打を契機に「2ボールだったのでストレートに絞って思い切って振った」と話した主将・片岡 尚哉内野手(4年=必由館)の適時打などで3点を先制。6回表にも1点を追加すると、先発・髙橋は高知大打線に最後まで的を絞らせず102球5安打奪三振4での無四球1失点(自責点0)完投勝利。救世主右腕の3勝目はそのまま、聖カタリナ大、悲願の初優勝に直結した。
蜂の巣をつついたような、しかし明らかに慣れていない歓喜の時間をしばらく過ごした。グラウンド整備とベンチ清掃に精を出すチームメイトを見やりながら2年秋から主将を務めている片岡はこうつぶやいた。
「優勝できた要因はやる気があるメンバーが残って、自分のやるべきことを練習でやってくれたからです」
かつての「アパッチ野球軍」的勢いはそのままに。野球の原理原則と絆を学んできた聖カタリナ大硬式野球部は、6月10日(火)神宮球場で9時から西南学院大(九州六大学野球代表)との全日本大学野球選手権大会初戦で、初の全国舞台を堂々と味わう闘いに挑む。















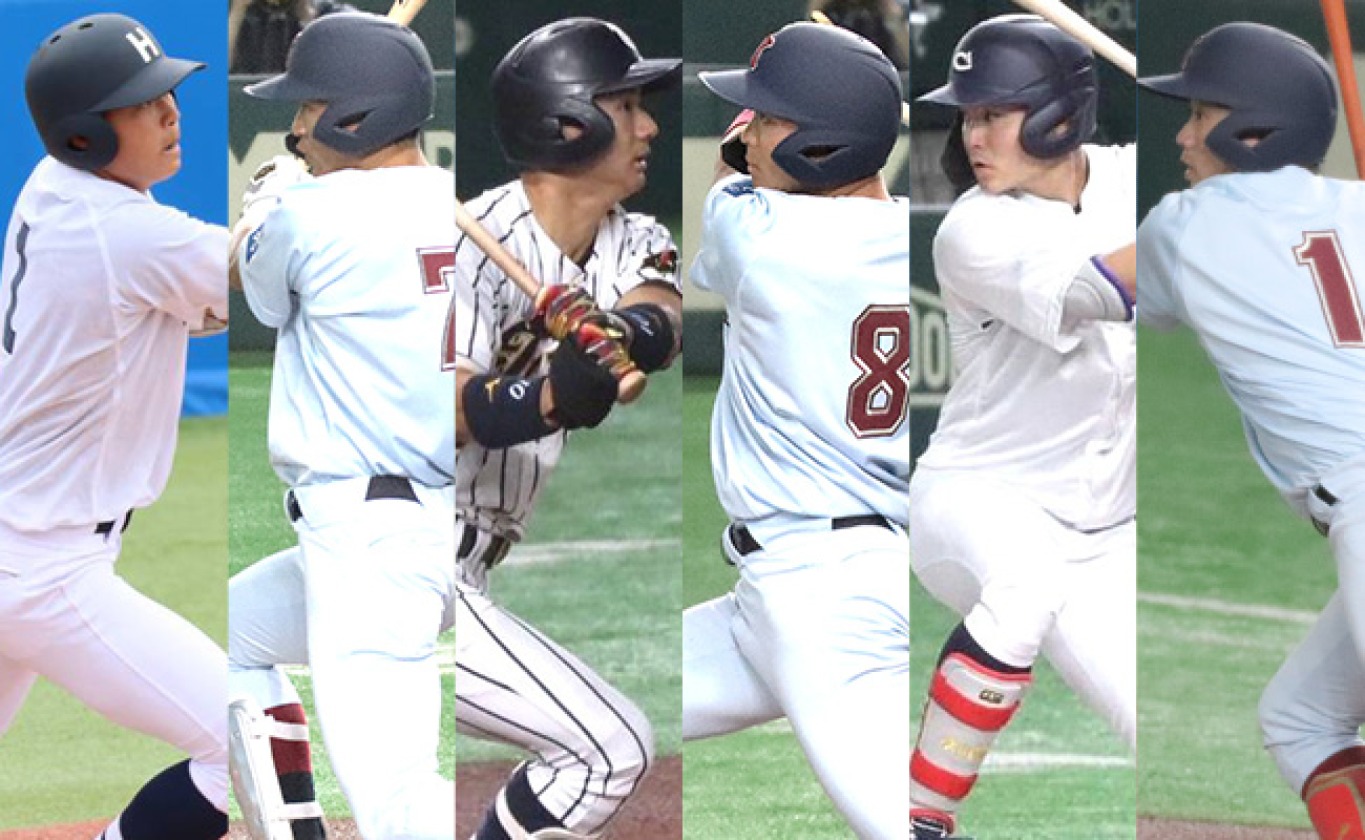
































この記事へのコメント
読込中…
読込中…
まだメッセージがありません。
>> 続きを表示