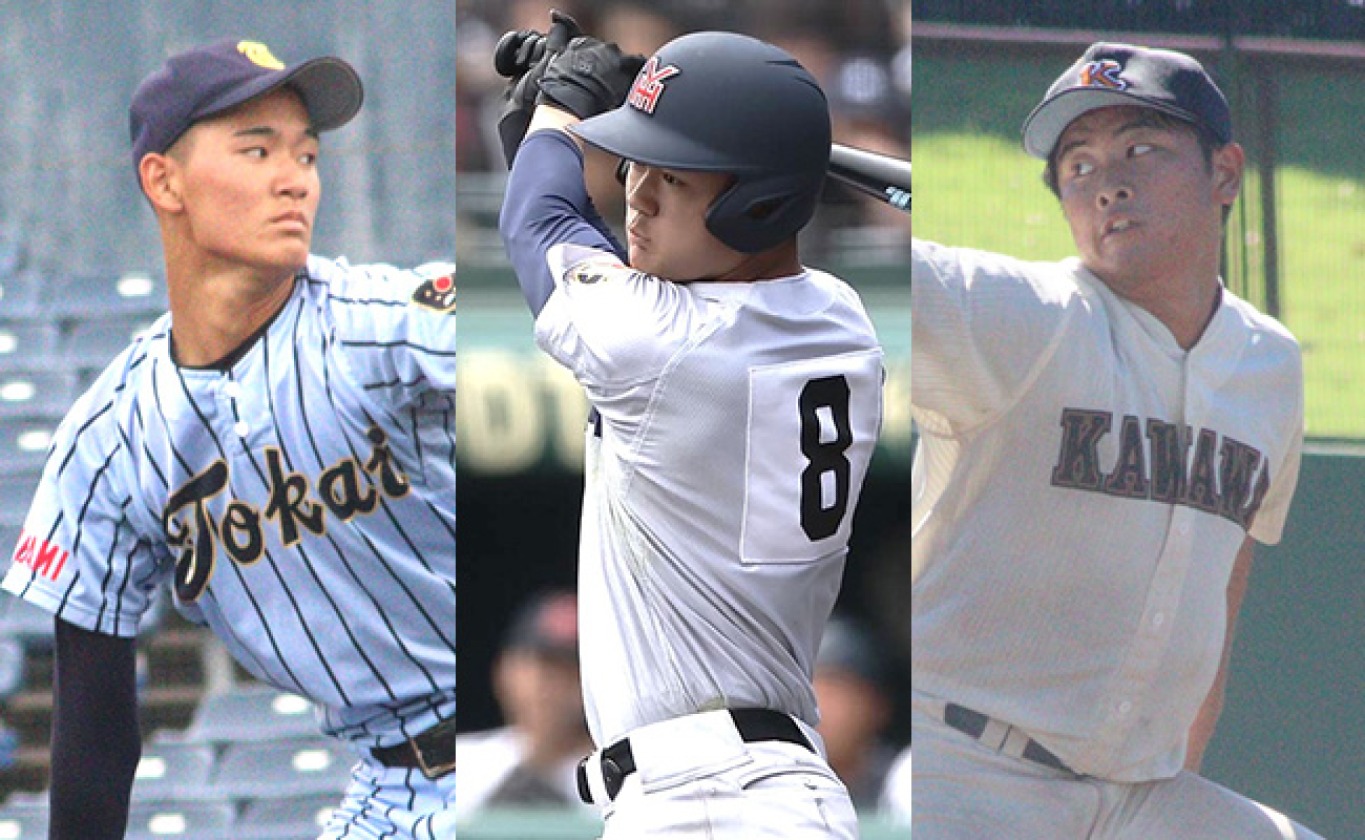定年退職→外部指導員はレアケース
近年、東京都の場合、教員の異動サイクルが短くなってきているという。チームに自分の理念や考え方を浸透させていくこと、それに基づいて中学や少年野球チームへ生徒募集をかけることが難しくなっている。
東京都に限らず、公立各校では、指導者の忌憚ない意見として、「自分が声をかけておいて、生徒が頑張って入試突破してきてくれたのに、自分が異動となっては申し訳ないし、責任が取れない」そういった嘆きの声も聞かれる。
例えば、夏休みに練習会を実施し、そこに参加してきた生徒で「いい選手なので、是非来て欲しいので受験してください」ということを伝えながら、いざ合格してみたら、声をかけてくれた指導者が異動となっていくというケースがあるのだ。選手やその親も、指導者側もどちらも落胆してしまう現実である。
この状況が続けば、部活動強化をしている私学との条件の格差がますます広がっていくことは否めない。
東京都では21世紀枠での甲子園出場に導き、夏の東東京大会でも2年連続で準優勝という実績を上げた小山台の福嶋正信監督や、片倉で西東京大会ベスト4進出などの実績を誇る宮本秀樹監督などのように定年退職後、外部指導員として監督を続けている人もいる。もっとも、これは稀有なケースでもあるといえる。
愛知でも実力校指導者が異動 高校野球の伝統とは何か
愛知県でも、西三河地区で暴れん坊として存在感を示すチームを作ってきた安城の加藤友嗣監督が豊田工科への異動となった。しかし、チームを引き継ぐのは責任教師として数年一緒にやってきた原田恭也監督だ。

シートノックを打つ加藤監督
「これまで以上にトリッキーにクセ者野球をやっていきます」と語る。チームカラーがしっかりと引き継がれそうな安城。西三河地区では新たな面白い対戦カードが起きそうな期待感もある。
かつて西三河地区では、東愛知大会準優勝や県大会ベスト4にチームを導いて、甲子園に手が届きかかった西尾東の寺澤康明監督が県教育委員会に異動となったこともあった。人事としては昇進ということになるのだろうけれども、部活動の指導現場を希望している身としては残念な思いがあるのも事実であろう。
東三河地区では豊橋工を2015年に21世紀枠で甲子園に導いた林泰盛監督が豊橋西に異動して後、コロナ禍で練習自粛の時期にも自前でブルペンを造ったり、グラウンド整備をしたりしながら環境を整えて豊橋西を作り上げてきた。そして、今年はその戦力も充実してきて手ごたえを感じていた勝負年だったが、このタイミングで異動となった。勤務先は母校の時習館となるが、所属は県教育委員会で中高一貫校推進チームとしての役割を担うことになって、直接野球部を指導することはなかなかできない状態のようである。
これも公務員としては昇進ということになるのだろうが、現場で部活動を指導していきたいという思いの人にとっては複雑な心境のはずだ。
中学校の現場では、教員の部活動での負担が多いということで、働き方改革が進められている。その中で、部活動の指導を地域に移行していこうという動きが極めて顕著になってきている。その波は、高校の現場にも及びつつある。その一方で、高校野球の指導をしたくて教員になったという人も多く存在している。
100年以上の歴史を有している高校野球である。学校である以上、選手が毎年替わっていくのは当然だけれども、チームを率いる指導者(監督)の思いは継承されていって欲しい。それが伝統を作り上げていくのではないか。かつて、高校野球では商業校が強かったのも、そんな伝統があったからである。
時代が変わっていくのは当然だ。しかし、高校野球を日本の継承文化の一端として捉えてみると、あまりにも杓子定規な人事異動で、部活動の現場が変わっていくということは大いに疑問を感じる。
そして間違いなく言えるのは、この人事問題が高校野球の私学と公立との格差を招いていることだ。新年度を迎えて、全国で教員の異動情報などを耳にすると、そんなことを考えざるを得ない。